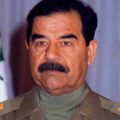アルコールや麻薬、ギャンブル依存については、なりやすい性格の系列化がなされていて、専用のリハビリ施設もある。
だがSNSは広まったばかりで、本格的な研究結果が出ていないのが現状だ。
なんせバーチャルゲームを五輪競技にするという動きもあるぐらいなのだから、SNS依存に対する対策が後回しになってしまうのも過言ではない。
米国NYビンガム大の情報経営学の准教授アイザック・バケフィは、在籍する大学の学生300人を対象に、SNS依存度を図るテストをアンケートを取り行った。
彼は、デ・ポール大のハームド・クアリ・サレリ博士を助手に統計を取り、学生の性格特性を、ゴールドバーグ博士が提唱した『ビッグファイブ』に分析したという。

©binghamton.edu
『ビッグ5』は日常のさりげない行動や習慣から、人の性格を読み取り、5つの要素を当てはめるという臨床心理学に基づいた性格分類法だ。
これにより、バケフィ准教授が調査を行った学生で、SNS依存者と思われる学生には『神経性』、『誠実性』、『協調性』の三つの性格が関連している事が判った。意外かもしれないが、アピールする事をよしとする外向性や、好奇心を満たしたい開放性が入ってない。
神経性が関係しているのは言うまでもない。日ごろのストレスや不安をSNSという名のはけ口に利用している人が多いからだ。

©binghamton.edu
私の友人には年代の違うSEが居るが彼らは職業柄SNS依存症だ。つぶやく内容も神経質そのもので、見る方からしてみればどうでもいい事だ。
『新幹線で前の客がシートを倒してきたのが腹がたった、オレを何だと思っているんだ』、『倒すのは客の権利だ』と喧嘩している様子を送ってくる中年SE、朝のトップニュースを見て自民党議員の対応のマジギレして自分の政治議論を熱くFBに長々と書く男性。一つ間違えるとモンスターである。
新幹線やバスなどの乗り物でリクライニングシートを倒すか悩んだことがある人は多いはず!そこであすは「リクライニングシートはどれくらい倒すのが適切なのか」をココ調するよ(⊃•̀ω•́)⊃✎⁾⁾
7時10分過ぎに放送予定☆#めざましテレビ pic.twitter.com/KmVOFfHSyb— めざましテレビ (@cx_mezamashi) 2017年4月9日
彼らに共通してるのは、イイネ+同意のコメントである。
誠実性と協調性に関しては、両方高くてもSNS依存になりやすいという傾向が発覚した。
人と関わる事を好み、目的意識の強い人がこれにあたるが、裏を返せば、さみしがりで負けん気が強い、強気の小心者になる。FB友達登録者が2000人を超えているのに、リアル友達の数は10人も居ないという人がこれに当たる。イイネの数は友達に比例しないのだ。
この手の人から年賀状毎年貰うのだが、文面はとんでもない事になっている。そのうちの一人は40代のマラソンランナーでFBの友達は5000人いるのだが、私の所に自分が思った事を全部書いてくるのだ。聞けばFBの5000人いる友達には本音を話せないのだという、逆効果だ。
話したいことありすぎて年賀状くそみたいに文長い人いるけどすまん…✋普通に話すか手紙遅れよって感じ…届いた人文句言っていいから最後まで読んで欲しい…
— 小宮 (@ko_miya17) 2014年12月27日
1つの大学に対しての調査であれば、信憑性はないと思われるので、もう一つ、米ミットウェスタン大が学生75人を対象に、どれだけFBに依存しているかを測定する『ベルゲン・フェイスブック依存症スケール』を使って行った研究に面白い結果が出た。
先程のバケフィ准教授も同じツールで学生にSNS依存度を図ったのだが、彼の場合は『FBを頻繁に使わないのであれば、タンブラー、インスタ、ツイッターなど他のSNSツールに置き換えて考えてくれ』と指示をだしたという。日本であれば、ここにLINE、ブログも加えて考えてみてほしい。
この依存症ツールは以下の質問項目に対し、1:全くない、2:ほとんどない、3:ときどき、4:頻繁、5:とても、と頻度を五段階に分けて答える様にしている。
1:FBに書きたい事や、その内容を常に考えている
2:FBを見たい、使いたいという衝動が起きる
3:嫌な事を忘れる為にFBを使う
4:FBをやめようと思ったが出来なかった
5:FBを使わないと落ち着かない
6:仕事や学業に支障が出るほど使ってしまう
よく考えればこれは、すべての依存症に言える項目で今更と思うのだが、ミッドウェスタン大は、この研究結果からさらに踏み込んだ。
バケフィ准教授は、SNS使用頻度の高い学生を性格分析したが、こちらはお金に対する概念を計ったのだ。
回答に答えた学生たちに対し、今すぐ7000円もらえる方を選ぶか、二週間後に22000円貰える方を選ぶか、選ばせたという。
すると3~6に対し、頻度が高く、依存度が高いと見られた学生程、先に7000円欲しいと答える結果が出た。つまり『目先の利益』を欲しがるという事になったのだ。
FBやLINEは、人間的距離感を保てば、無害なだけでなく有益なツールになるはずである。メールやHPの利用からネットに入った人たちは、そう思っているだろう。
だがSNS=共感をインスタントに得られるツールとして使っている人にとって、SNSは依存症になりやすいものだというだけでなく、目先の利益にとらわれ、将来への投資を怠る人間にしてしまうという事が今回の研究結果で明らかになった。

©natanaelginting
ネット黎明期から使ってきた身として、メールやネットが定額制になった時はありがたかった。FAXを使わなくて済む上、送った送らないといもめ事からも解放される上、会社での自由時間も確保できた。
だがSNSは『即レスしないと不愛想な人と思われる』という脅迫概念すら持ち込んでいる様に思える。
必要とあれば距離をとって利用する事が大事なのではないだろうか。
A COMBINATION OF PERSONALITY TRAITS MIGHT MAKE YOU MORE ADDICTED TO SOCIAL NETWORKS
Facebook addiction is associated with impulsive decision-making, study finds